総合文化財センター常設展示室の期間展示コーナーを更新しました
常設展示室に期間展示コーナーを開設しました
「早池峰の自然・文化・歴史・人」「埋蔵文化財」の二つのテーマから、企画展などで紹介した資料を展示します。
期間展示は、3か月程度で展示替えを行います。ぜひ、ご覧ください。
令和7年度の予定
|
期 間 |
期間展示コーナー1 早池峰の自然・文化・人 |
期間展示コーナー2 埋蔵文化財 |
|---|---|---|
| 6月から8月 | 早池峰山植物関係資料 | 滝大神1遺跡(東和地区) |
| 9月から11月 | ベルンドルフ関係資料 | 久田野1遺跡(花巻地区) |
| 12月から2月 | たばこ史料館関係資料 | 小田遺跡(大迫地区) |
| 3月から5月 | 山岳博物館関係資料 |
田屋遺跡(石鳥谷地区) |
期間展示コーナー1 早池峰の自然・文化・人



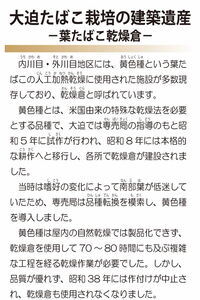
大迫たばこ栽培の建築遺産ー葉たばこ乾燥倉ー
内川目(うちかわめ)・外川目(そとかわめ)地区には、黄色種(おうしょくしゅ)という葉たばこの人工加熱乾燥(じんこうかねつかんそう)に使用された施設が多数現存しており、乾燥倉(かんそうぐら)と呼ばれています。
黄色種とは、米国由来の特殊な乾燥法を必要とする品種で、大迫では専売局(せんばいきょく)の指導(しどう)のもと昭和5年に試作(しさく)が行われ、昭和8年には本格的な耕作(こうさく)へと移行し、各所で乾燥倉が建設されました。
当時は嗜好(しこう)の変化によって南部葉(なんぶは)が低迷していたため、専売局は品種転換(ひんしゅてんかん)を模索(もさく)し、黄色種を導入しました。
黄色種は屋内の自然乾燥では製品化できず、乾燥倉を使用して70~80時間にも及ぶ複雑な工程を経る乾燥作業が必要でした。しかし、品質が優れず、昭和38年には作付けが中止され、乾燥倉も使用されなくなりました。
期間展示コーナー2 埋蔵文化財



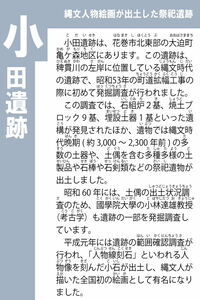
縄文人物絵画が出土した祭祀遺跡
小田遺跡(こだいせき)は、花巻市北東部(はなまきしほくとうぶ)の大迫町亀ケ森地区(おおはさままちかめがもりちく)にあります。この遺跡は、稗貫川(ひえぬきがわ)の左岸(さがん)に位置している縄文時代(じょうもんじだい)の遺跡で、昭和53年の町道拡幅工事(ちょうどうかくふくこうじ)の際に初めて発掘調査(はっくつちょうさ)が行われました。
この調査では、石組炉(いしぐみろ)2基(き)、焼土(しょうど)ブロック9基、埋設土器(まいせつどき)1基といった遺構(いこう
)が発見されたほか、遺物では縄文時代晩期(ばんき)(約3,000~2,300年前)の多数(たすう)の土器や、土偶(どぐう)を含む多種多様(たしゅたよう)の土製品(どせいひん)や石棒(せきぼう)や石剣類(せっけんるい)などの祭祀(さいし)遺物が出土しました。
昭和60年には、土偶の出土状況調査(しゅつどじょうきょうちょうさ)のため、國學院大學(こくがくいんだいがく)の小林達雄教授(こばやしたつおきょうじゅ)(考古学)(こうこがく)も遺跡の一部を発掘調査しています。
平成元年には遺跡の範囲確認調査(はんいかくにんちょうさ)が行われ、「人物線刻石」(じんぶつせんこくせき)といわれる人物像(じんぶつぞう)を刻(きざ)んだ小石(こいし)が出土し、縄文人が描(えが)いた全国初の絵画(かいが)として有名になりました。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
花巻市総合文化財センター
〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第3地割39番地1
電話:0198-29-4567 ファクス:0198-48-3001
花巻市総合文化財センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
