大迫町郷土いろはかるた(前半)
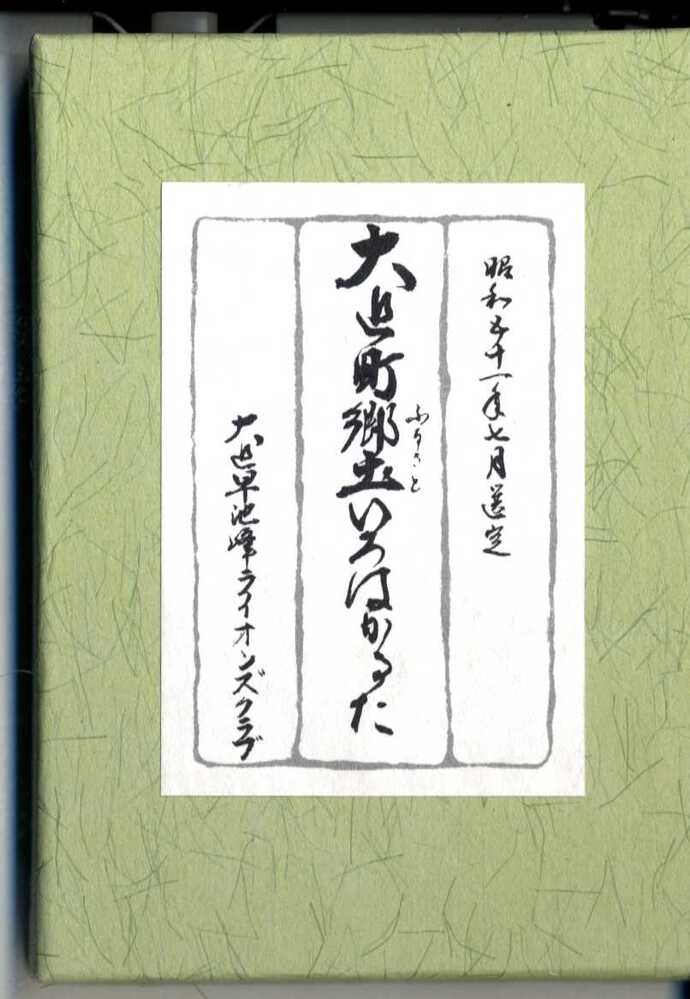
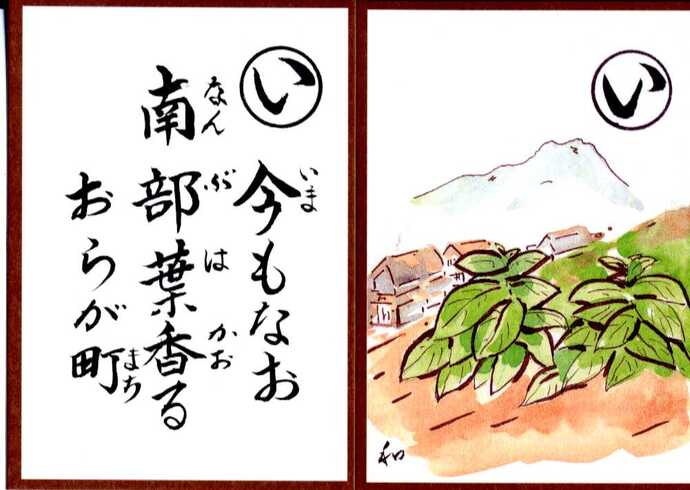

湯だんご・・そば粉を練っただんごで、ゆでてネギ味噌で食べる。
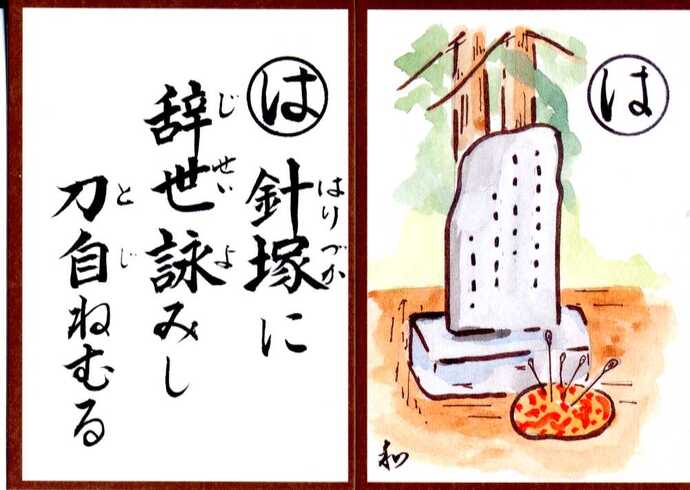
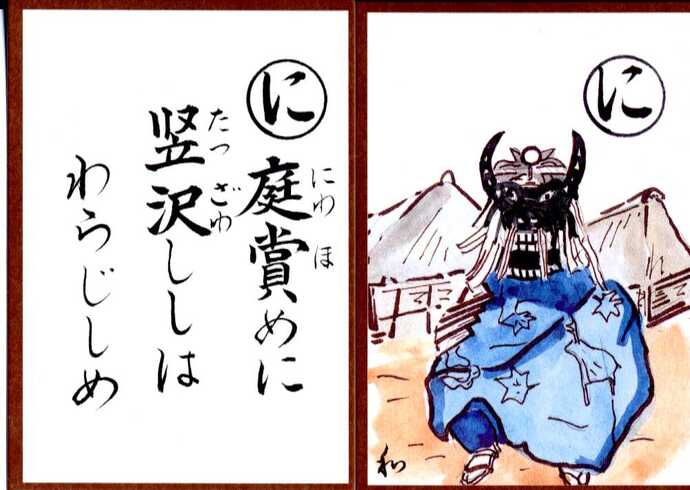
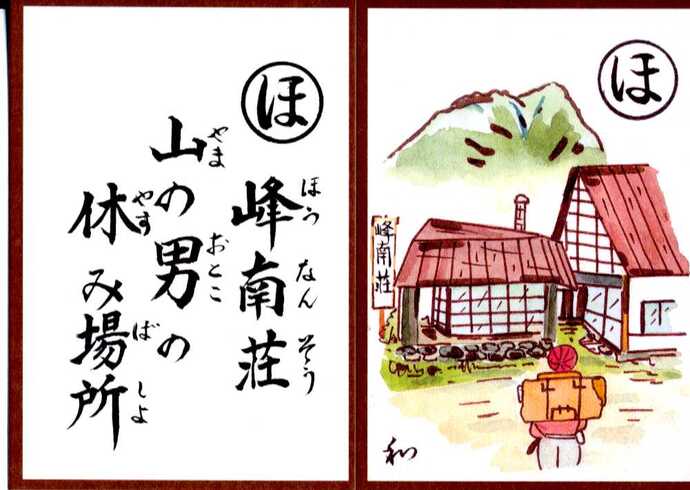

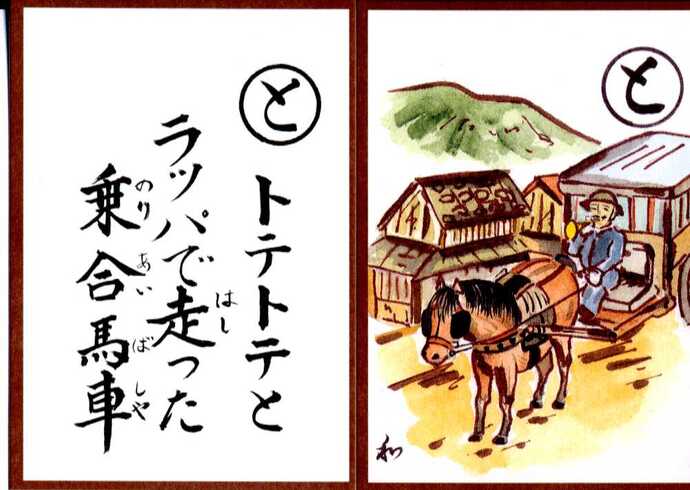
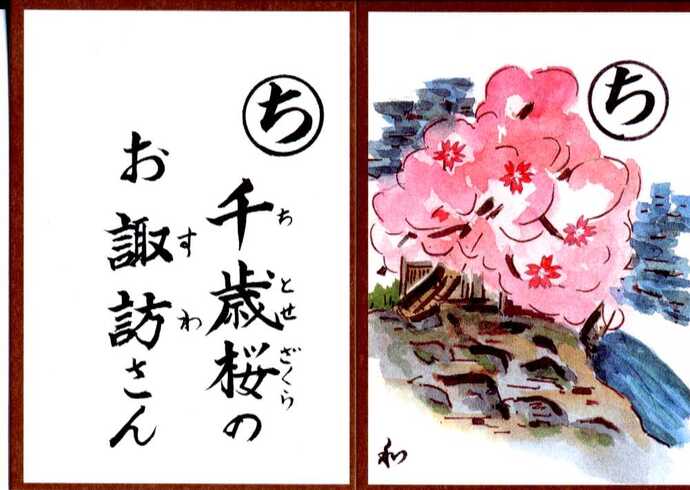
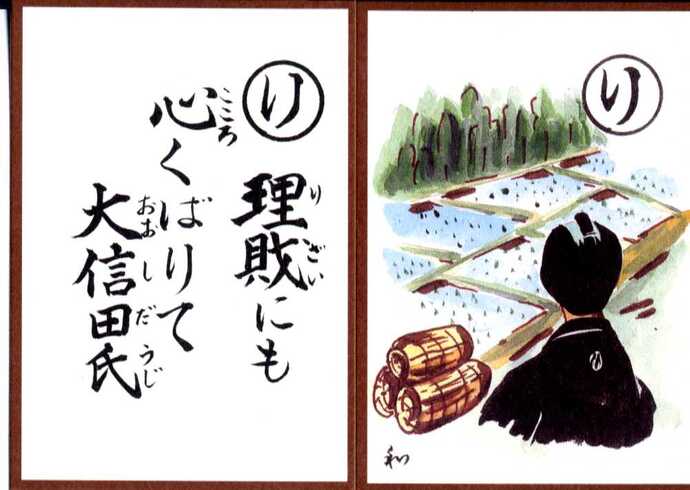
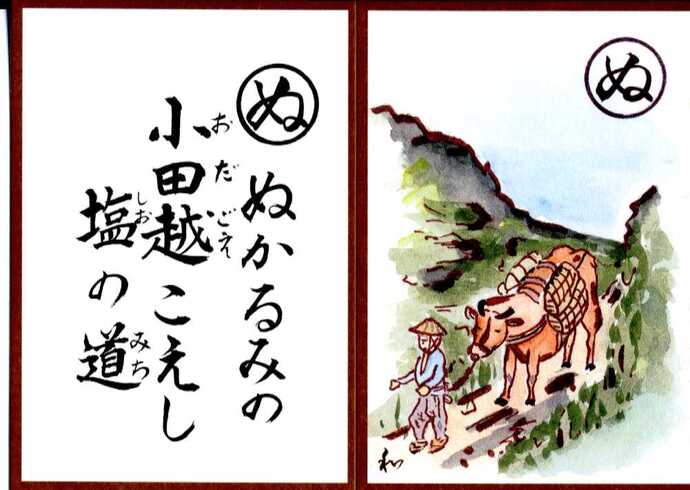
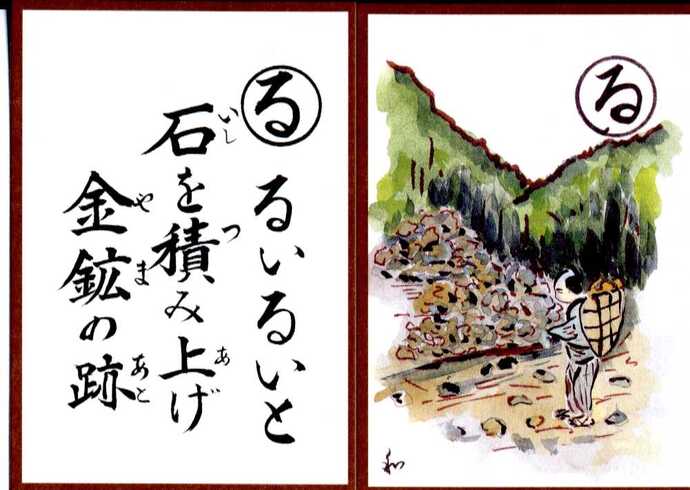
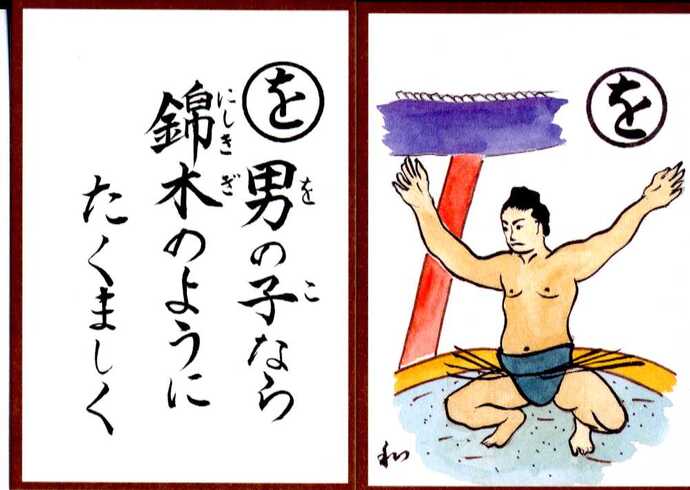
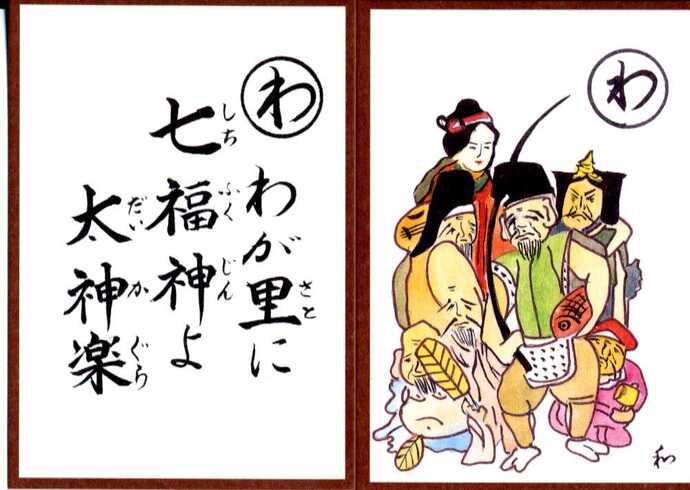
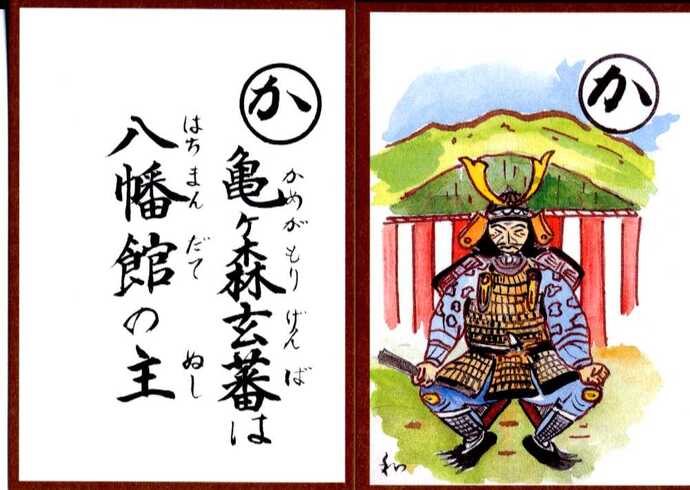
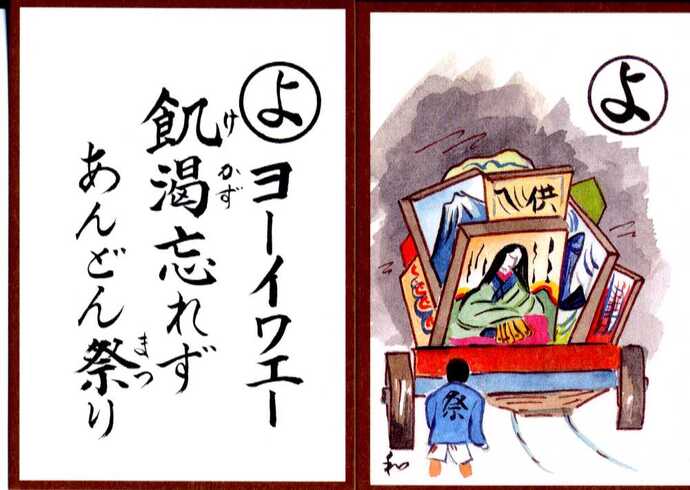

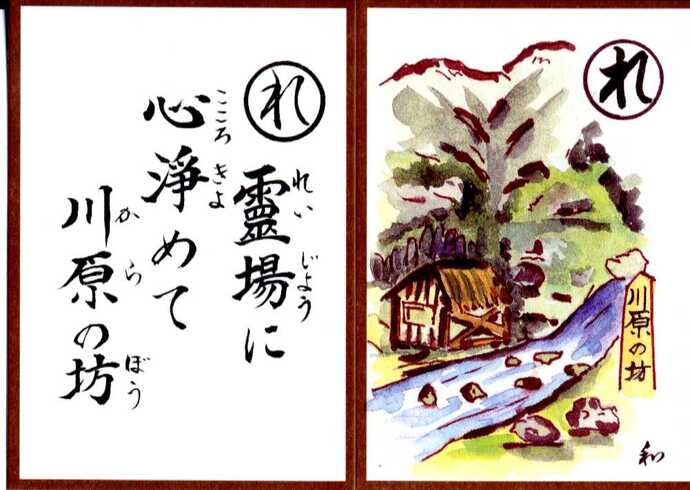
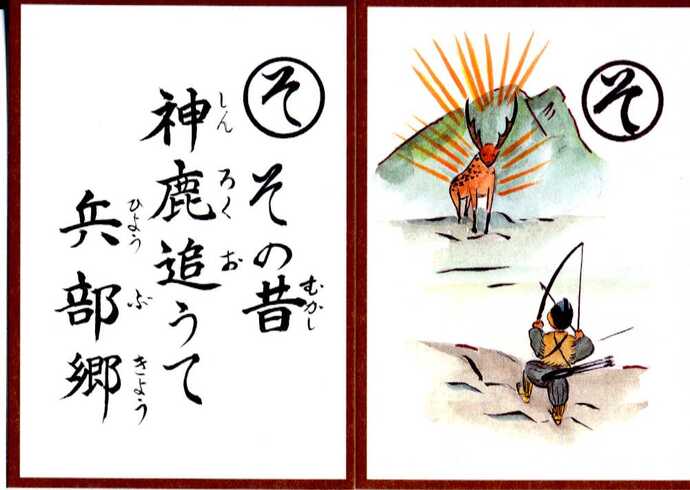
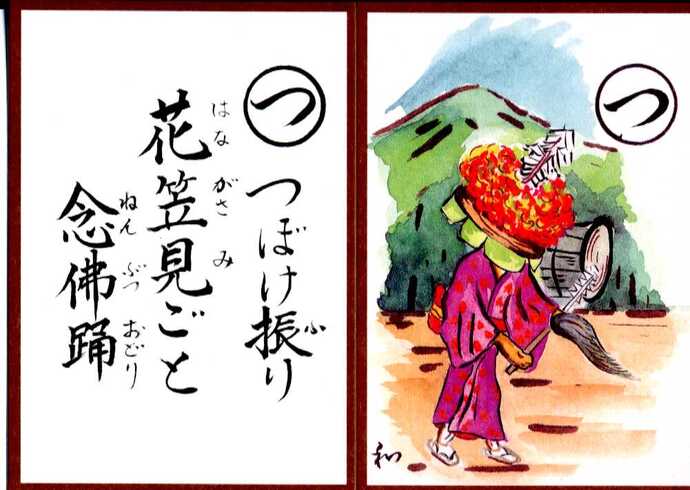
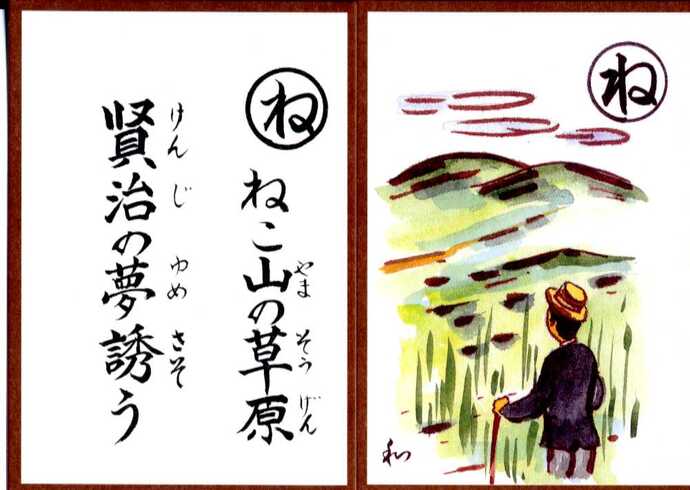
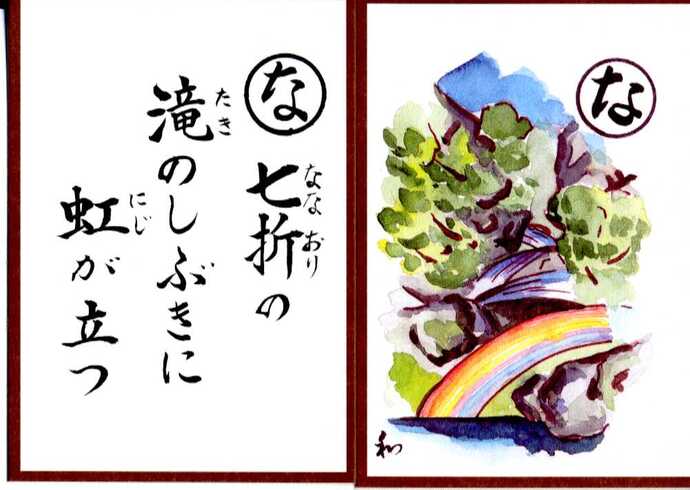
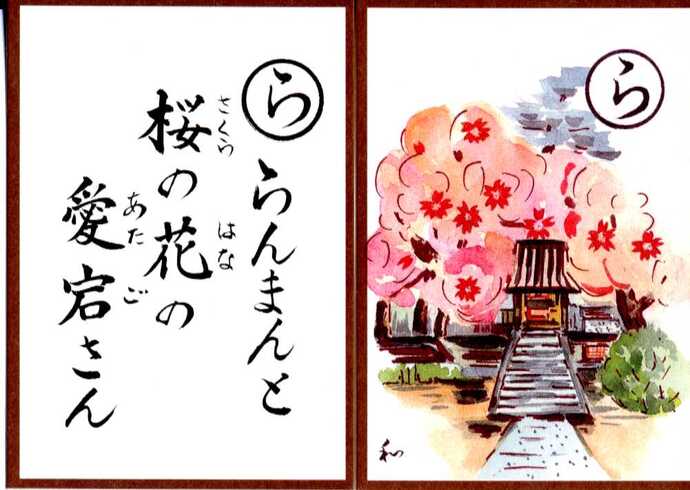

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
大迫小学校
〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第18地割3番地
電話:0198-48-2226 ファクス:0198-48-4146
大迫小学校へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
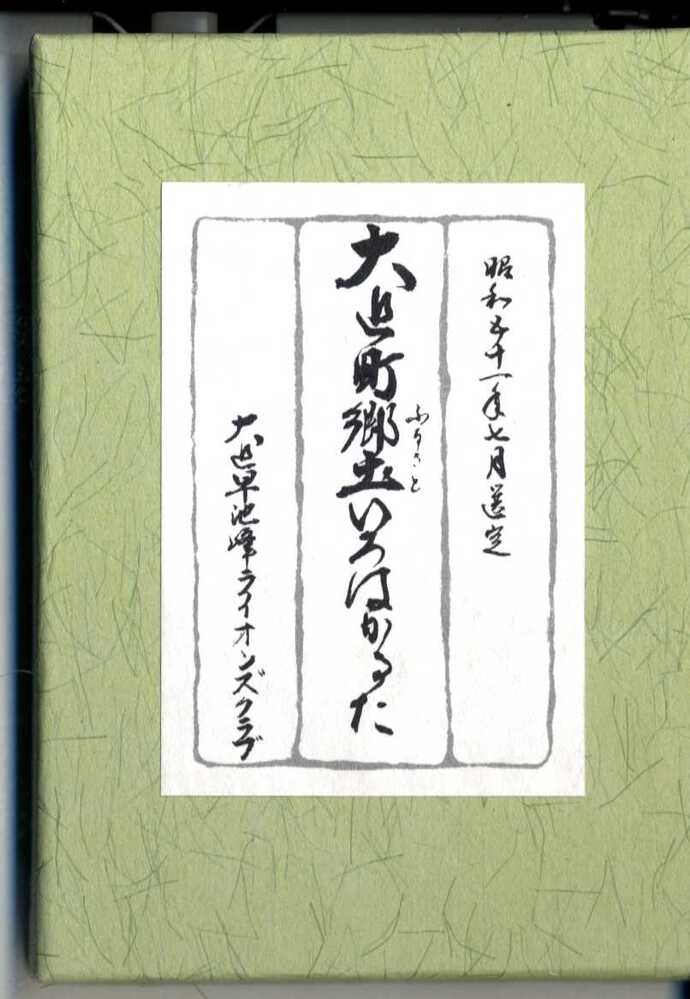
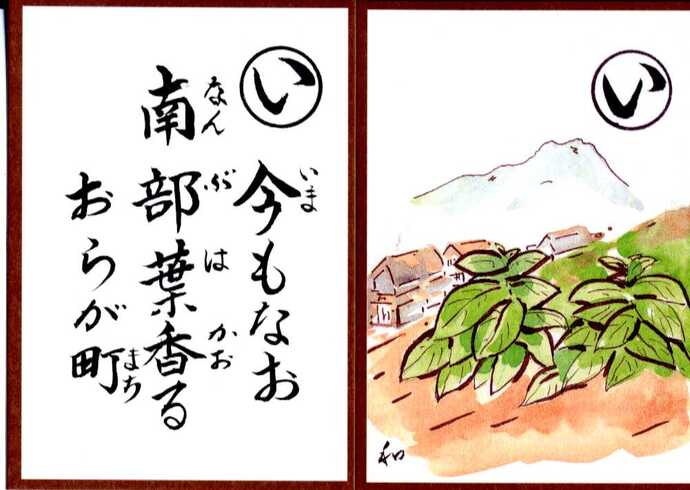

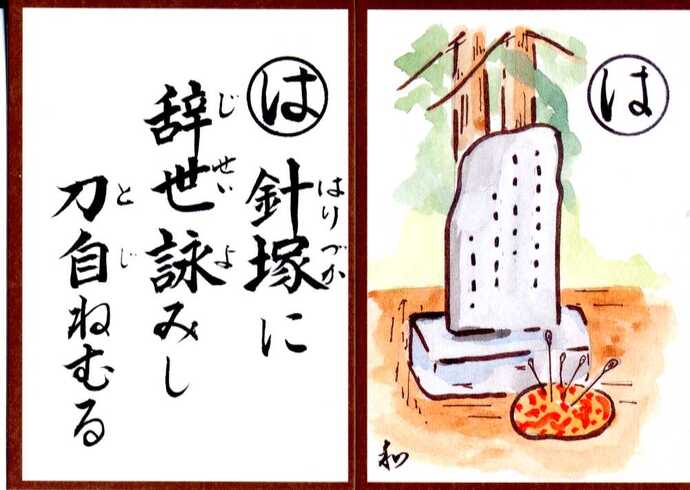
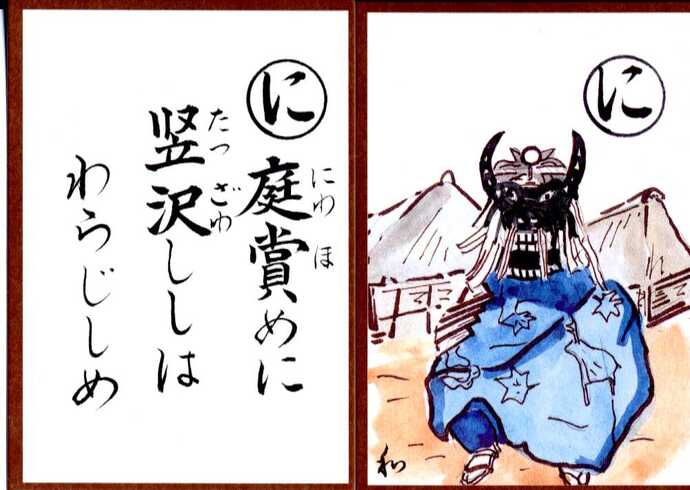
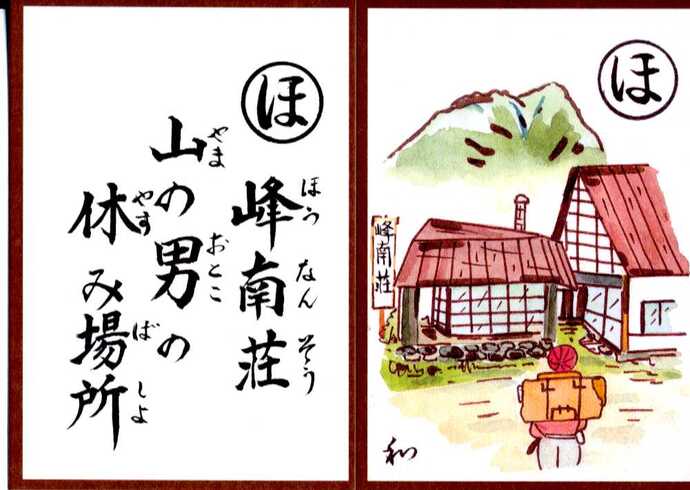

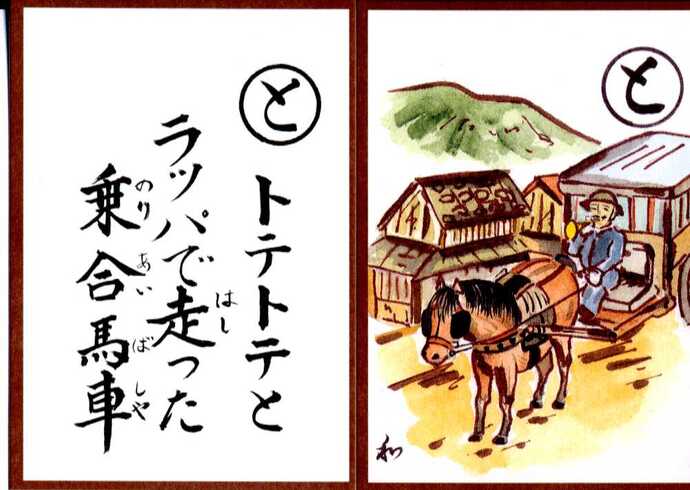
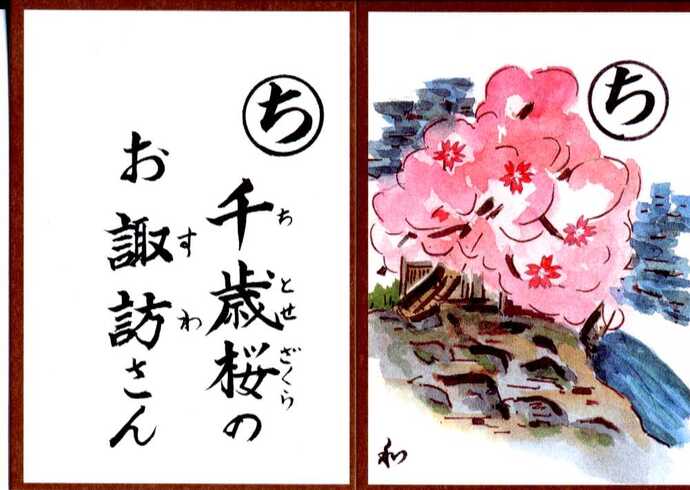
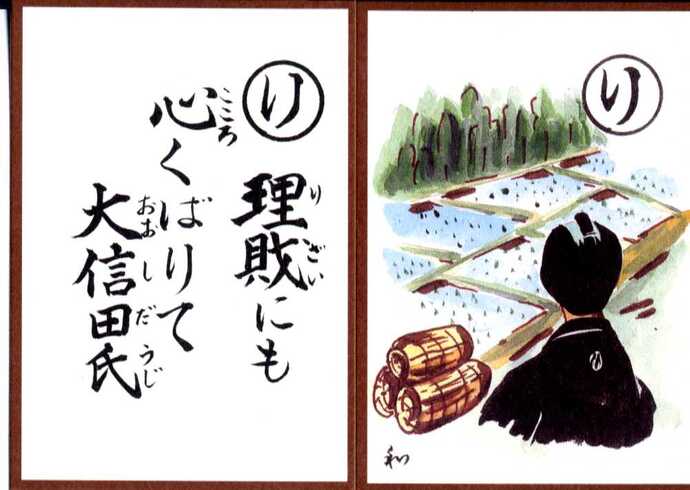
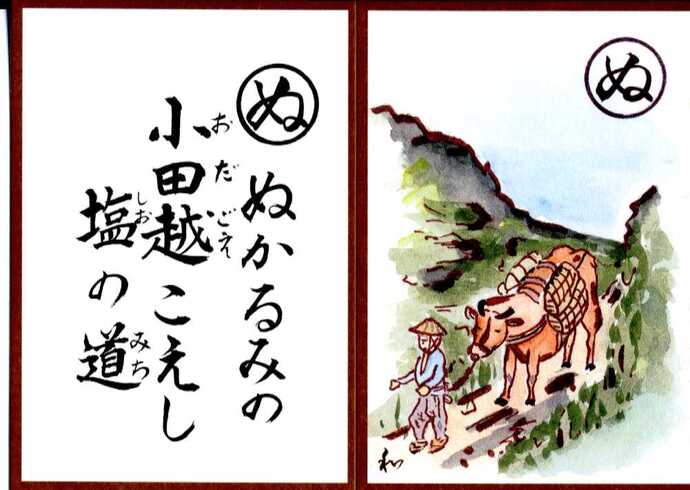
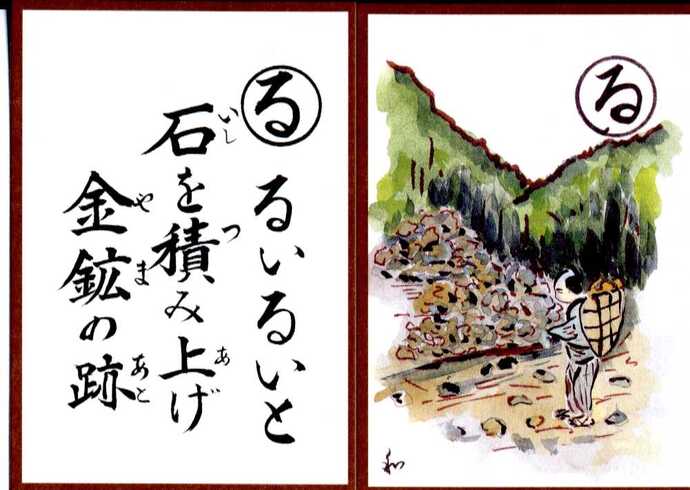
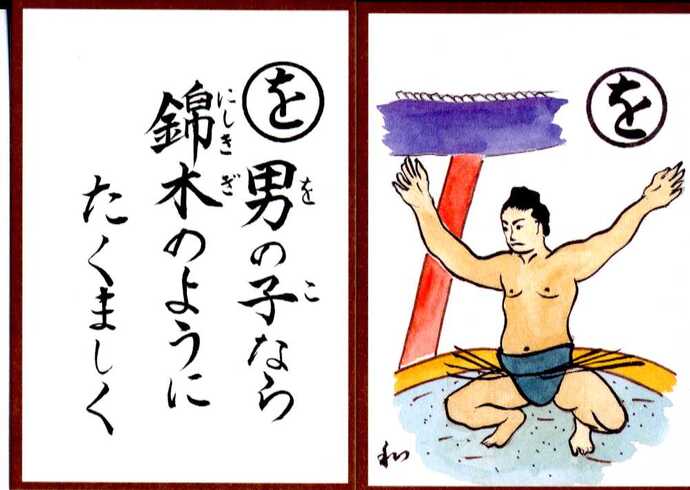
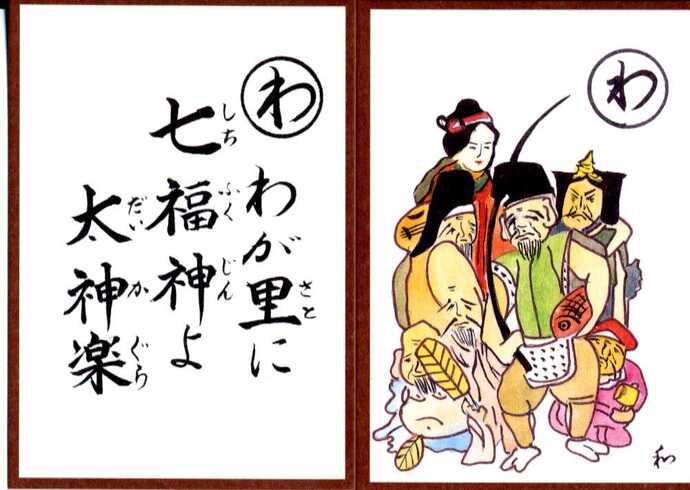
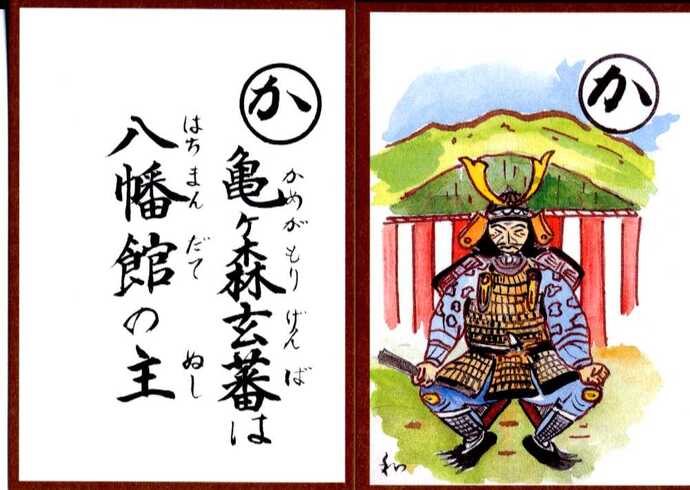
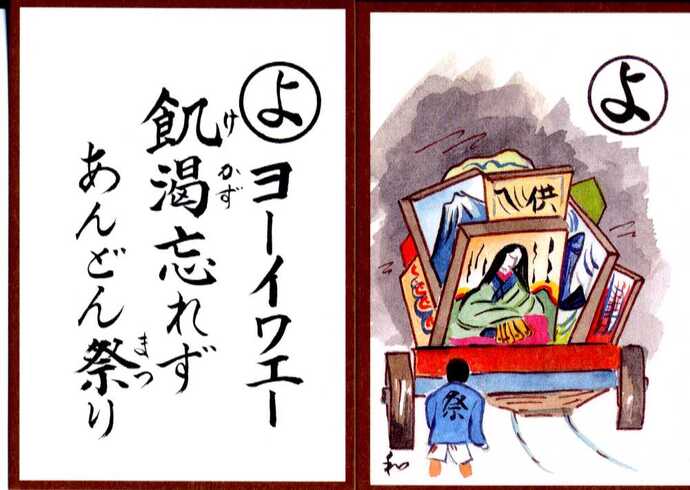

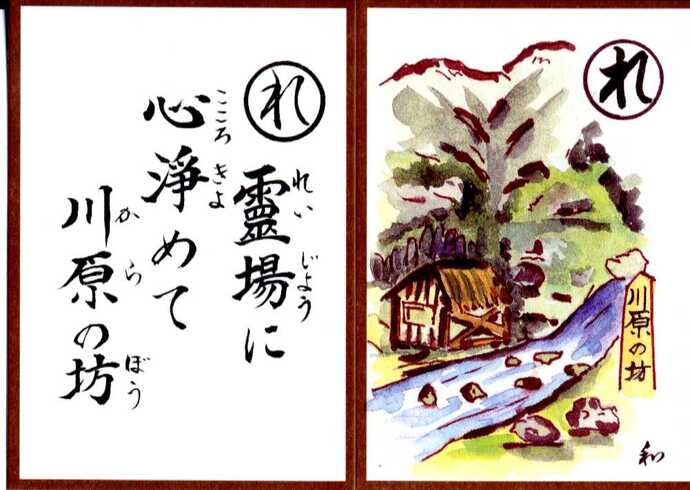
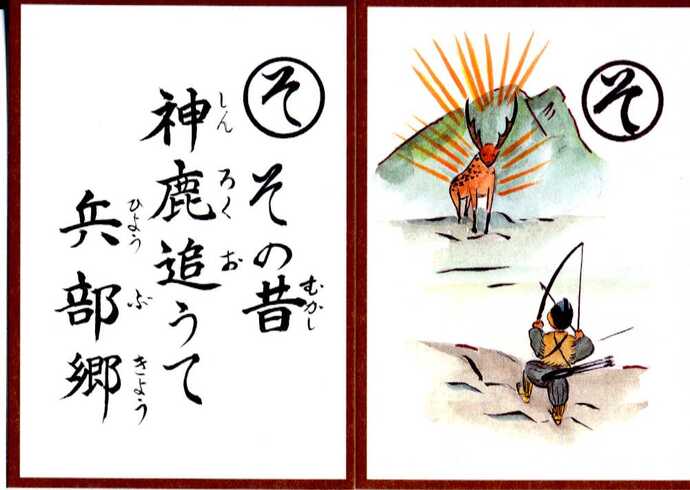
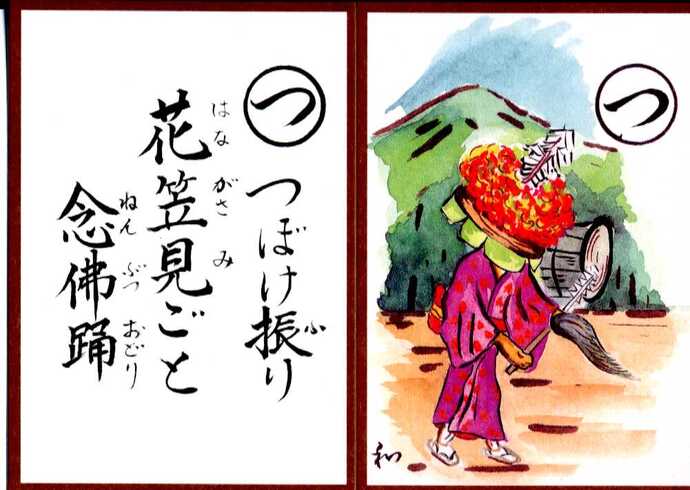
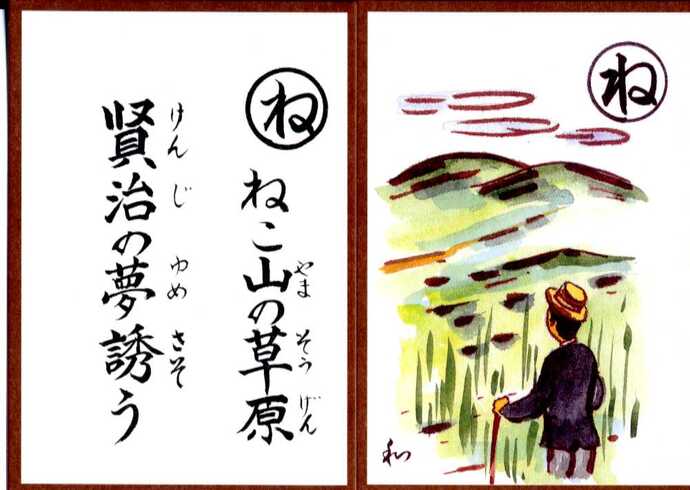
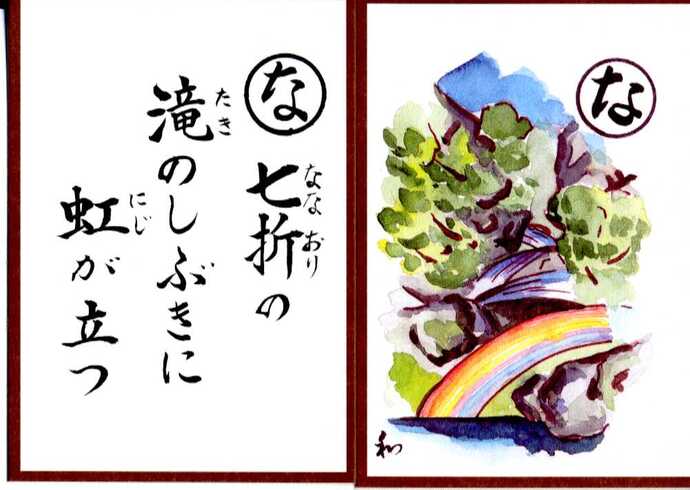
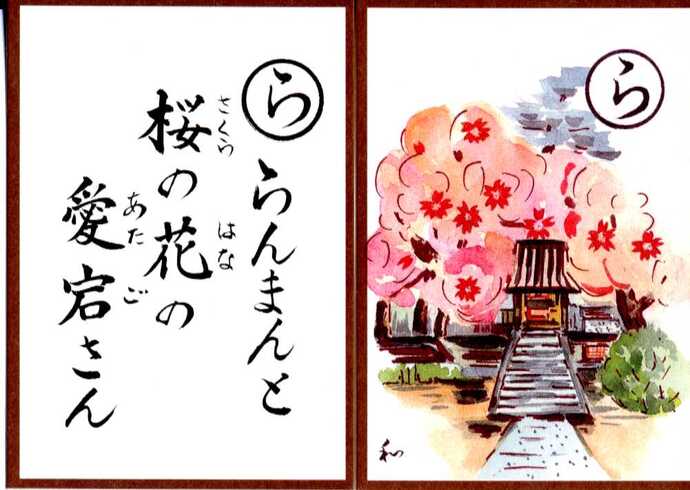

大迫小学校
〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第18地割3番地
電話:0198-48-2226 ファクス:0198-48-4146
大迫小学校へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。